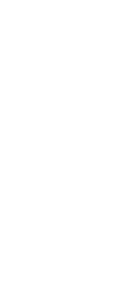活動内容

エネシフ湖北/ともすラボ 年間報告会&ワークショップ~ステークホルダーミーティング~
※今回は学生ライターに記事執筆を依頼しました。
みなさん、こんにちは!学生ライターの大同です。
今回は、2025年2月15日(土)にえきまちテラス長浜にて開催された「ステークホルダーミーティング(エネシフ湖北・ともすラボ主催)」の様子をお届けします。
(※記録ムービー)
これまでエネシフ湖北では、「ゼロカーボン×〇〇」をテーマに、様々なミートアップを開催してきました。今回はそれらの総まとめの報告と、次のステップに向けたワークショップが開催されました。
この日は長浜に住んでいる人だけでなく、地域外の方もたくさん参加されており、その数、30名以上!
長浜の地域課題の中には地域内でできることもあれば、地域外と協力してできることもあります。
自分の立場からできることを見つけ、つながり、次の一歩を進めたい
という目的のもと、会はスタートしました。
1週間前の大雪とはうって変わってよいお天気になりました!
オープニング
はじめにエネシフ湖北からのお話です。
エネシフ湖北の活動の背景や、地域で脱炭素に取り組むことの重要性についての説明がありました。
脱炭素やエネルギーは硬いイメージもあり、世界規模の話であるがゆえに、どこから取り組んでいけばよいのか難しいと感じることもあると思います。
しかし、実は地域にとっては劇的に変わっていける「きっかけ」でもあるということでした。
脱炭素の視点は、地方の課題を突破できるひとつの切り口になるという思いで、取り組んでいるということです。
そんなエネシフ湖北のモットーとなっているのが「灯台もとテラス」。

エネシフ湖北代表の清水さんは、
「地域にある資源や本来持ってる価値は昔から変わっていないはずで、それをどうやって磨いて繋いでいくかを考えている。
当たり前すぎて見落としている地元の人や資源にスポットライトを当て、あしもと、地元を照らしているようで、でも気づいたら、未来を照らしている。そんな活動をしていきたい」と。
地域でできること、解決できることと外に頼ることを分けて取り組んでいくことが、地域づくりに通ずるところだとお話がありました。
これまでのミートアップの紹介
続いて、これまで行われてきたミートアップの紹介がありました。
地球温暖化というと、一気にハードルがあがり、関われる人が限られてしまう気がします。
しかし、「ゼロカーボン×〇〇」にすることで、多様な人と関われる場を作ることができたということでした。
伊香高校断熱改修ワークショップの紹介
エネシフ湖北では、何かをやりたいプレーヤーを支援する中間支援組織としての役割も担っていきたいと考えているとのことです。
その一例として断熱改修ワークショップの紹介がありました。
伊香高校では校長先生や担当の先生の熱い思いがきっかけとなり、エネシフ湖北や地元の工務店と協力して、教室の断熱改修ワークショップを2回開催してきました。
断熱改修によりエアコンの使用量が減ったり、快適な教室になったりするだけでなく、生徒のキャリア教育としても重要な役割をはたしているということでした。
この日参加されていた校長先生からは、
「ワークショップ1日目と2日目では全然顔つきが違った。
今年卒業する生徒の中には、高校生活で一番楽しかったことがこのワークショップだと話してくれた人もいた。」
とのお言葉がありました。
これには会場からも思わず拍手が。
(株)日産自動車からの発表
(株)日産自動車の東郷さんからは、地域との連携の事例としてちょうちん祭りへの参加報告がありました。
ちょうちん祭りは、2024年9月、長浜市の北に位置する西浅井町の中学校で行われたお祭りです。地域の中学生が企画したということで、地域の人も大勢参加するお祭りということでした。
そしてこのお祭りの特徴のひとつに、提灯の電気は街で作られた再生可能エネルギーを利用したことがあげられます。
日産自動車は、会社としてカーボンニュートラルへの取り組みを促進しており、
そのひとつが電気自動車の普及活動です。
今回のお祭りでは、日産の電気自動車にためた電気で提灯に明かりを灯しました。そしてそのためた電気は西浅井で発電されたものだそうです。
東郷さんは、お祭りを通して満足度も高く、EVの認知度向上にもつながったとお話されていました。
地元にとっては地域の活性化につながり、企業にとっては自社の技術を使い広められる、
それぞれがWin-Winの関係になれる、そんな事例でした。
ワークショップ
休憩を挟んだのち、琵琶湖環境科学研究センターの木村さんの進行により、ワークショップが始まりました。
今回のワークショップのテーマは地域資源と地域コミュニティのつながりを可視化することです。
琵琶湖環境科学研究センターでは、地域資源から地域課題を考えるワークショップを各地で行なっています。
滋賀県の朽木や高島という地域でも行なっているようで、今回はその事例をご紹介いただきました。
木村さんは、地域資源と地域コミュニティは相互に関係しており、地域にある課題はすべてなにかしら繋がっているとおっしゃっていました。
地域の人と一緒に、それぞれのつながりを洗い出し、誰がどういう立場から関われるのかを「ステークホルダーシナリオ」としてまとめていった事例のお話もありました。
事例紹介の後は、そのシナリオを長浜でも作っていくためのはじめのステップとして、
2つのテーマに分かれて課題感や参加者それぞれの立場からの意見を共有しました。
① 地域に眠るエネルギーを掘り起こし価値を生む
② 森林(山・木・水・空気・動物)の循環が持つ価値を活用する
最後にそれぞれのグループで出た意見を共有しました。
①のグループからは、
地域のエネルギーとして、森林は大きなポテンシャルを持っていること、さらに「エネルギー」として地域の次世代をどう巻き込んでいくかも重要であるという意見がありました。
まさかの始めから森林と地域のエネルギーは深く関係しているというワークショップの核心にせまる気づきが出て、非常に盛り上がったそうです。
②のグループから共有された意見の中では、
水や大気の循環や森林の成長は、住んでいる環境や関わり方によって、その時間軸の感覚は異なるよねという声が印象に残っています。
だからこそ、この地域に住んでいない企業の方などが、実際に森の資源を訪れて体験してみるような機会があれば、
より具体的に考えられるといった意見も出ていました。
最後にまさかの・・・
ワークショップも盛り上がって終了かと思いきや・・・
「みなさん、今そこでお米が炊きあがりました!ゲリラ炊飯です!」
ゲリラ炊飯…??
なんと、最後に用意されていたのは、ネガティブに捉えられがちな農業を面白くポジティブに伝えよう
と活動する「RICE IS COMEDY」によるゲリラ炊飯でした!
「ゲリラ炊飯」は告知もなしに突然街中でお米を炊いて、炊きたてのご飯で作ったおにぎりを振る舞うという企画だそうです。
外にでるとお米の良い匂い。
釜のふたをあけるぱっかーんの儀とともに姿を見せたのは、長浜市西浅井町産の「いのちの壱」。
できたてのおにぎりをほおばりながら、私のところではこれできますよ、
次こんなイベントやってみましょうよと、次につながる話が飛び交っていました。
今回のワークショップをきっかけにまた新しい動きが起きそうな予感がします!
(それにしてもあのおにぎりは今まで食べた中で一番おいしかった…。)
今回のステークホルダーミーティングの報告はここまでとなります。
長くなりましたが、最後までご覧いただきありがとうございました!

京都大学農学部森林科学科3年。気候変動問題に関心があり、最近は地域のポテンシャルを活かした課題解決の面白さに気づいて、勉強中。